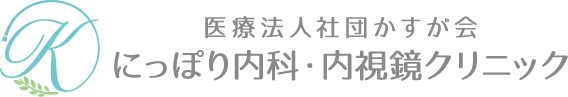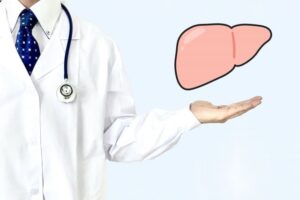肝臓の主な疾患
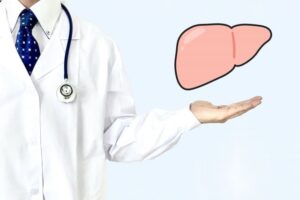
肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、初期の段階で症状は現れず、自覚症状がない場合がほとんどです。気付いた時には進行していたケースも珍しくありません。
肝炎ウイルス(B型肝炎(HBV)、C型肝炎(HCV))の感染や、長期の過度な飲酒が主な原因で、肝炎から肝硬変へと進み、肝がんへと病状が悪化していきます。重篤な状態になる前に、初期の段階で発見することがとても大事です。
肝炎
肝炎とは肝臓の炎症のことで、肝炎ウイルスの感染、アルコールの過剰摂取、肥満など、様々な原因で起こります。急性肝炎と慢性肝炎に分けられており、急性肝炎は6ヶ月以内に落ち着くものをいい、6ヶ月以上の期間持続する肝炎を慢性肝炎といいます。慢性肝炎で軽い肝炎が長期に続く場合、症状はあまり認めません。しかし10年、20年あるいはそれ以上続き、肝臓に線維(コラーゲンなど)が蓄積し、肝細胞が再生する力を失うと肝機能が低下してきます。こうして肝硬変に進行します。
慢性肝炎では皮膚のかゆみを伴うことがあります。炎症が強い場合には倦怠感を認めることがあります。急性肝炎で短期間に炎症が起こる場合は、発熱、のどの痛み、頭痛、体のだるさなど、かぜのような症状を認めることがあります。食欲低下、吐き気、腹痛を感じることもあります。また、血液中のビリルビン濃度の上昇により、黄疸が出現し、皮膚や白目の部分が黄色くなったり、尿が濃い茶色になったりすることがあります。皮膚に発疹がみられることもあります。
劇症肝炎(急性肝不全)は、肝臓の機能が急激に低下し、意識障害などの重篤な症状が現れます。全身の臓器に障害を起こしやすいため、肝臓に対する治療だけでなく、呼吸や循環などの全身的な管理が必要になります。
B型肝炎
B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することによって起こります。血液感染(輸血や出産、刺青、針刺し事故など)や性交渉などによることもあります。出産後や乳児期に感染すると高率に慢性化し、肝硬変、肝がんへと進展する場合があります。症状としては全身のだるさ、食欲の低下、吐き気、嘔吐、褐色尿、黄疸などが出現します。
B型慢性肝炎では徐々に肝臓が破壊されていくため自覚症状が現れないことが多いといえます。成人で感染した場合はB型急性肝炎となり、一部は劇症化(重症の肝炎になり、肝不全により死に至る)することがありますが、多くは治癒します。B型肝炎に対してはインターフェロン治療や核酸アナログ製剤が有効であり、病態に応じて使用されています。
C型肝炎
C型肝炎ウイルス(HCV)の感染によるもので、血液を介して感染します。感染しても肝炎は重症化せずに、急性肝炎としての自覚症状がない場合もあります。劇症化することはまれですが、感染後に約70%は慢性肝炎に移行するとされています。C型慢性肝炎では、肝臓で炎症が持続することにより、肝硬変に進行したり、肝がんができやすくなったりします。肝硬変や肝がんに進展する最も大きな要因といわれています。
C型肝炎では、かつては副作用の強いインターフェロン治療が積極的に行われていましたが、近年では副作用の少ない経口薬(直接作動型抗ウイルス薬)が登場し、ほとんどの患者様でウイルスを排除できるようになっています。
アルコール性肝障害
アルコール性肝障害は常習的に飲酒している方に発症する病気です。飲酒によりアルコール性脂肪肝になり、さらにアルコール性肝炎に進展します。治療せず放置し大量飲酒を続けると、肝炎が長く続くことによって肝硬変や肝がんに進行する場合もあります。治療は原因が飲酒であることから、禁酒が原則となります。禁酒により約30%の方の肝臓は正常化し、約10%は悪化して、肝硬変へ進行するといわれています。
脂肪肝
中性脂肪が肝臓に多く蓄積した状態となるのが脂肪肝です。過食や運動不足、飲酒などが原因としてよく知られています。健康診断などで指摘されることも多い病気ですが、脂肪肝だけで症状が現れることはほとんどありません。
今まで、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)と呼ばれていた飲酒しない人の脂肪肝は、2023年から新たに**代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD: Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease)と呼ばれるようになりました。この中には、肝炎が持続し、徐々に線維化が進行する代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH: Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis)**という病態が含まれます。
MASHでは、肝炎が進行することで、肝硬変や肝がんに至る可能性があるとされています。そのため、早期の診断と治療が重要です。肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病との関連性が非常に強いため、生活習慣の改善が有効な対策とされています。
診断には、血液検査や画像診断(超音波検査、MRIなど)がまず行われますが、MASHを確定診断するためには肝生検(肝臓の組織を採取して調べる検査)が必要です。この検査によって、炎症や線維化の程度を直接評価することが可能です。
肝硬変
肝硬変とは、肝硬変の状態になると肝臓が変形してしまい、肝機能も元通りには戻らなくなっていきます。肝硬変はさらに進行すると肝不全となり、また食道・胃静脈瘤による吐血、腹水貯留による腹部膨満や足の浮腫、肝性脳症による意識障害などの合併症を来すこともあるため、生活指導を含めた定期的な管理が必要となります。
肝臓がん
肝臓がんは、肝臓にできるがんのことです。肝臓は体の中で食べ物を消化したり、毒を取り除いたりする大事な役割を持っています。肝臓がんは、肝臓の細胞が異常に増えて、塊(がん細胞)を作ることで進行します。主な原因は、肝炎ウイルスやアルコールの飲みすぎ、肥満などです。症状としては、腹部の痛みや食欲不振、体重減少などがあります。早期に見つけて治療することが大切ですが、進行すると治療が難しくなることがあります。